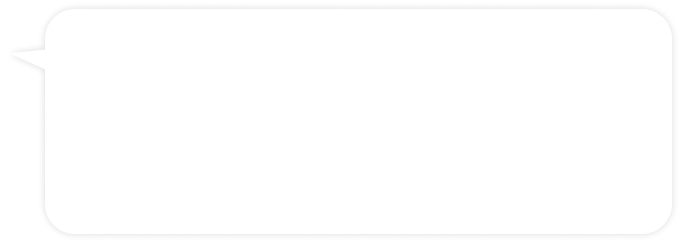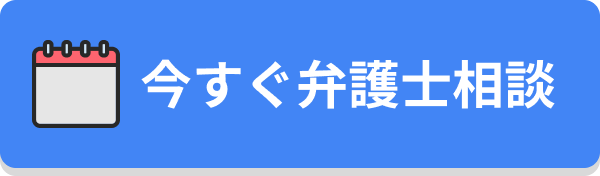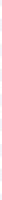離婚したくてもできないあなたは必見!離婚できない理由4つと対策
離婚できない理由は何ですか?離婚したくても離婚できない人・夫婦には、何かしらの理由があるはずです。気持ちは既に離れてしまっているのに、結婚生活を続けるのは苦痛でしょう。その「離婚したくてもできない理由」に対応するための対策をご紹介します。

離婚できない理由とその対策
相手が離婚に反対している
離婚は両者の合意によって成り立つため、相手と話し合いができなかったり、離婚の同意が得られなければ、原則として離婚することができません。
交渉の余地がないか弁護士に相談するのが良いでしょう。
弁護士に相談を
どのような条件なら離婚してくれるかわからない、相手が感情で離婚を拒否している、モラハラ・DVで支配的な環境になっている場合は弁護士にご相談ください。
実は、法的に離婚できる場合がある
相手が離婚に同意しない場合でも民法に定められた法定離婚事由に当てはまる場合は裁判による離婚が可能です。詳しい条件は後述します。
経済的な不安
配偶者の収入に頼っている人は、経済的な理由から離婚できない場合が少なくありません。
出産を機に収入が下がってしまった場合も離婚後の生活がしづらくなることが考えられます。
この対処法としては以下が考えられます。
実家に頼る
実家が残っていれば、住居と生活基盤は確保できるため一時的でも頼ることをお勧めします。
離婚後にもらえるお金について検討する
夫婦で築いた財産があれば、離婚の際に財産分与で共有財産を得ることができ、子供がいれば、養育費を受け取ることができます。
ただし、現金・預金などの資産がない配偶者から相場通りの財産分与を受けたり、収入の少ない配偶者から多額の養育費を支払ってもらうことは難しいです。そのため、現実的に支払える金額や支払い方法で解決するのが望ましいです。
公的支援を受ける
- 児童扶養手当
- 児童育成手当
- 住宅手当
- 医療費助成
- 児童手当
- 生活保護
経済的困窮に対する公的支援として、上記のものが知られています。まずは公的機関で調べてみることをお勧めします。自治体によってさらに充実した社会保障を提供している場合もあります。
【関連記事】 離婚後にもらえる手当とは?シングルマザーの離婚後の不安を解決!
仕事をする
経済的自立のためには忙しくても仕事をする必要があります。子育てをしている場合は、子育て支援に積極的な企業で働くのが望ましいです。
まずは、ハローワークへの相談をお勧めします。
子どものことが心配である
子どもの生活環境が変わってしまうことや、子どもに与える精神的な影響も考えて離婚したくてもできない方もいると思います。
ただ、仲の悪い夫婦でいることが子供にとって最善とは限りません。離婚のメリットとデメリットを検討しましょう。
対処法としては以下が考えられます。
子の福祉に配慮した離婚を
養育費で経済面で子供の生活を守るのはもちろんとして、子供は父母どちらと暮らしたいか、面会交流の頻度はどのくらいが望ましいかなど配慮することが望ましいです。
子どもを信じ、適切な説明をすることも大事
あなたが考えているよりもずっと子どもは夫婦のことをよく見ています。
無理をして離婚を我慢するよりも、子どもはあなたと一緒に家を出たいと考えているかもしれません。
有責配偶者である
不倫をしてしまった、暴力を振るってしまったなど離婚になってもおかしくない状態を作ってしまった配偶者を有責配偶者と言います。
有責配偶者が相手の同意なしで離婚することは原則できませんが、昭和62年の最高裁判決にて離婚できる可能性が認められています。(この判決は破棄差し戻しの元、平成元年に東京高裁で離婚請求が認められています)
一 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない。
引用:裁判要旨
法的に離婚できる条件とは
民法770条では以下の離婚事由が定められています。これらは法定離婚事由と呼ばれ、該当する事実がある場合は配偶者の同意なしで離婚が可能です。
法的な妥当性は裁判で判断されますが、裁判の結果が見えるほどの証拠を示せれば、協議や調停の段階で相手に離婚を納得させることも可能です。
配偶者に不貞な行為があったとき。
配偶者が第三者と性的な関係を持つことを指します。これは、配偶者の信頼を大きく裏切る行為とされています。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者が自分を無視し、経済的な援助や生活上の配慮を放棄した場合を指します。夫婦には同居・協力・扶助の義務があるのです。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
配偶者の生死が不明で、その状態が3年以上続いている場合を指します。
配偶者の強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
配偶者が重度の精神疾患に罹患し、その回復が見込めない場合を指します。ただし、強度の精神病であることや看病などの努力をしたことが条件となります。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
上記4つの事由に離婚原因が該当しない場合、5号「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうか争うことになります。
DVを受けている事実があったり、長年別居中であれば認められやすいのですが、性格の不一致などでは認められにくいのが現状です。
離婚を認めてもらうためには弁護士に相談を
裁判所に離婚を認めてもらうためには、婚姻関係が破綻しているということを論理的に粘り強く主張していかなければなりません。
婚姻関係の破綻については、明確な定義づけがされておらず、おそらく裁判の中でも何をもって婚姻関係が破たんしていると主張しているのかが問われることになります。
まとめ
離婚したくてもできない理由がある方は、その不安要素を解決することが必要です。
離婚の決断をし、離婚したい理由が明確で、かつ離婚事由に当てはまっている場合は、すぐに弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
また、金銭面・子どものことが気になって離婚に踏み切れないという理由がある方も、弁護士に相談することによって解決できるかもしれません。