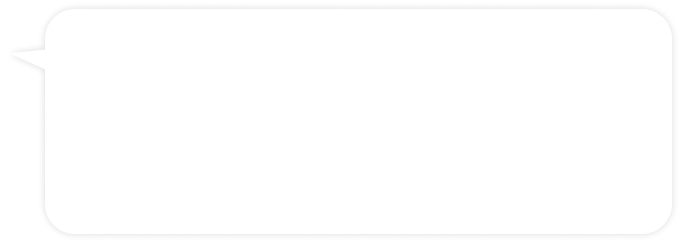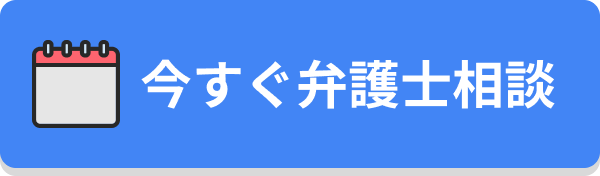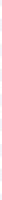公正証書は取り消しや無効化、変更ができる?公正証書作成時に必ず注意すべき点と無効・変更主張方法について解説
離婚時に作成した公正証書の取り消しや無効化、変更はできることがありますが、簡単に行うことはできません。今回は公正証書の変更・公正証書の取り消し・公正証書の無効主張について詳しくお伝えしたいと思います。「公正証書の内容を無効化したい・変更したい」と考えている方や、「相手から公正証書を無効にしてくれと言われているが、無効にしたくない」という方は必見です。

「公正証書を作成する際に必ず注意すべきことを知りたい」
「公正証書を作成したけれど内容の変更や無効化、取り消しを行いたい」
というお悩みを抱えている人は、弁護士へ相談することで下記のようなことを実現できる可能性があります。
弁護士に相談・依頼するメリット
・夫婦間で作成した公正証書の内容について問題がないか、法的な観点から確認してくれる。作成時の注意点を教えてくれる。
・依頼をすれば公正証書を作成してくれる。
・あなたの場合、公正証書の変更や無効化、取り消しが可能か判断してくれる。また、場合によっては変更や無効化を実現するための手続き、交渉等も代理で行ってくれる。
カケコムでは、あなたにあった弁護士を見つけるサービスを提供しています。
公正証書の取り消しはできる?無効主張や変更はできる?

パートナーとの離婚は結婚するよりも数倍大変だと聞いたことはありませんか?
実際に離婚の際に決めておくべきことは多々あり、この取り決めをきちんとしておかないと後々、トラブルに発展することがあります。
そのために公正証書として親権や養育費、共有財産などの取り決めを記しておくことが大切です。
もっとも、離婚をするにあたって作成した公正証書ですが、基本的には取消や変更は出来ません。 国の機関である公証人が法律に基づいて厳正な手続きを踏んで作成するためです。
例えば、民事裁判でこの公正証書を提出すれば、裁判官は有効な証拠として採用することが多いでしょう。
公正証書というのは、高い証明力を有しているため、簡単に取消したりすることができないのです。ただし、場合によっては取り消しが可能となることもあります。詳しくは後述しますので、ご一読ください。
公正証書とは?3つの解説

この記事で紹介していく公正証書についてどのような内容が記載されているのか、ご存知でしょうか。
まずは公正証書について詳しくお話し致します。
公証人が作成する書面
公証事務とは国民の権利義務に関係し、私的紛争の予防の実現を目指すものです。
「子供の親権や養育費に関して」「慰謝料に関して」「財産分与に関して」などの取り決め内容が記載された離婚協議書の効力を強めることができます。
また、支払いが滞ったときや約束事が守られなかったときに、裁判をすることなく相手の財産に強制執行をかけて差し押さえをすることができます。
公正証書については以下の記事も参考にしてみてください。
強制執行の根拠になるなど、強い効力を持つ
パートナーと公正証書を作成することで、相手側が約束した内容の支払いに応じなかった場合に、裁判を起こすことなく強制執行をかけることが可能です。
公正証書なく慰謝料などの支払いを要求しても、「そんな約束をした覚えはない」と支払いに応じない可能性もありますから、この強制執行をかけられる点が最大のメリットということができます。
記載されている意思内容も、簡単に翻すことができない
公正証書は公証人が法律に違反していないかどうか、当事者双方が内容に理解をし合意をしているかどうかを、厳格な手続きを経て作成されるため、簡単に意思内容を翻すことは出来ません。
公文書のため、原本は公正役場に20年間保管されるため、内容を変更したり取り消したりする場合は、基本的には一から作成し直さなければいけないのです。
公正証書を作成する際に必ず注意すべき点
公正証書は前の項目でご説明した通りの効力を持っていますが、作成する際に注意すべきことがいくつかあります。
ご自身が公正証書にどのような効力を求めているかに合わせて、下記の注意点を取り入れていってみてください。
公正証書を作成する際の注意点(1) 強制執行を想定しているなら強制執行認諾文言を記載すること
例えば養育費の支払いについて公正証書に定め、未払いが発生した場合は公正証書をもとに強制執行を行いたいと考えているとします。
そのような場合は、公正証書の内容に強制執行認諾文言を必ず記載しておきましょう。強制執行認諾文言付きの公正証書でなければ、強制執行の手続きを行うことはできません。
公正証書を作成する際の注意点(2) 過不足ない文言で構成文書を作成すること
公正証書を作成したものの、具体的な金額が書かれておらず内容が不十分であったり、記載している文言が曖昧であると、望んでいた通りに公正証書の効力が発揮できない可能性があります。
公正証書を作成するからには、過不足ない内容を記載しなければあまり意味がありません。
そのため、公正証書を作成する際は夫婦だけで行うのではなく、合意内容を決める段階で弁護士に相談をするほうが、全体的・長期的に見て得をするということが十分に考えられます。
思い当たる状況があれば、いち早く弁護士に相談し、どのような法的問題が発生し得るか・どのように対応すべきかを確認するのも一つの手です。
弁護士に依頼すれば、公正証書の作成についてだけではなく、離婚に関する話し合いのサポートや代理交渉を行ってくれる場合もありますので、あなたに有利に離婚を進めるためにも一度下記ボタンよりご相談ください。
公正証書を作成する際の注意点(3) 公正証書の送達証明書をもらっておく
公正証書を書いたら、早めに公正証書の送達証明書をもらっておくことも重要です。送達証明書をもらっておくことで、強制執行の手続きを行うことが可能になります。
送達証明書をもらうには、公証役場に送達の申請を行いましょう。この際、特別送達という送達方法を利用する必要があります。
そもそも公正証書の無効化・取消しは可能なの?

公正証書の効力が絶大で法に基づいて作成されたものだとお話ししましたが、取り消ししたい場合はどのような手続きを踏めばいいのでしょうか。
錯誤による無効・詐欺による取消し・脅迫による取消しなどを主張すること自体は可能
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。出典:民法
但し、当事者に重過失が認められた場合は、無効を主張することができません。
また民法96条により、詐欺もしくは脅迫による意思表示は取り消すことができる、と定められています。
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。出典:民法
公正証書上の合意についてこれらの無効・取消しを主張することを禁止する法律はありませんので、錯誤や詐欺、脅迫等があった場合には、民法95条や96条を根拠にすることで、公正証書の無効や取り消しを主張することができます。
公正証書に記載されている内容について調停・裁判により争うこともできる
公正証書で合意した内容を調停・裁判で争ってはならないという法律はありませんので、理論上は、公正証書の内容の取り消しや無効、大幅な変更について、調停や裁判で争うことが可能です。
例えば、「慰謝料や養育費を一度は承諾したが、高額過ぎて支払いが困難のため安くしてほしい」「養育費を求めないと約束したが、やはり請求したい」等のケースが挙げられます。
しかし理論上は調停や裁判で争うことが可能でも、争う際の問題点はあります。それは、公正証書の無効や取り消しはそもそも認められづらいということです。詳しくは次の項目でご説明します。
公正証書の場合、無効や取消しが認められづらいことに注意
公正証書上の合意は、法律の専門家である公証人が公証している合意であり、その証拠が公正証書として明確に残っている以上、錯誤や詐欺や強迫などがあったという主張が認められにくくなることに注意が必要です。
公証人は元裁判官などの法律実務経験を有した法律に関するプロです。
弁護士に依頼をしたとしても、公正証書の無効や取り消しは難しい案件といえます。
費用が高額になる可能性もある上に、必ず無効にできるとは限りませんのでしっかり考えてから裁判を起こすようにしましょう。あなたの場合、無効にできる可能性があるのか一度専門家に確認してみたい場合は、下記のボタンより弁護士相談を行ってみてください。
初回のご相談を無料で受け付けていたり、弁護士費用を分割払いで支払うことが可能な事務所もありますので、お気軽にご連絡ください。
公正証書の内容に不満がある場合には

公正証書は変更や取消は出来ないものとして考えた上で作成しましょう。
ですが、養育費など支払う側の生活環境の変化で内容を一部変更したい場合もあります。
公正証書の取消ではなく変更の場合はどのようにすればいいのでしょうか。
公正証書の内容の変更に同意してもらうよう、相手を説得する
公正証書の内容変更で多い事例が、養育費の金額の変更です。
例えば、勤めていた会社が倒産してしまったり、リストラにあってしまって所得が大幅に減少した場合や、再婚によって養うべき家族が増えたことで養育費の負担が厳しくなった場合です。
このようにやむを得ない事情により、公正証書の内容を変更したい場合は、まずは相手の同意を得るために協議をすることが重要です。
公正証書の内容は当事者の合意ですから、内容を変更する合意がある場合には当然内容を変更できるのです。
なお、協議が成立しない場合には、調停での話し合いや裁判に進むことになるでしょう。
そもそも公正証書を作成する段階で慎重に考える
公正証書の内容の変更を求める側は自己に有利に変更したいと思うものですから、説得がうまくいくケースは多くはないでしょう。
また、上述のとおり、無効や取消しの主張も簡単にはいきません。
そのため、そもそも公正証書を作成する段階で相手と内容について慎重に協議し合い、その後に取消や変更の手続きが必要ないようにすることが一番です。
早期に弁護士に相談することが最適
公正証書の内容は家族の将来に関わる大切なものです。
不備があると後々の後悔に繋がりますので、早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。
また、一刻も早く手続きを終えて離婚届を提出したい方も少なくはないはずです。
今回の記事で見たように、公正証書は慎重に作らなければなりません。
公正証書を作成した後にトラブルが起きることを極力回避できるよう、専門家を交えて適切な内容で公正証書を作成していきましょう。
公正証書の取り消しはできる?|公正証書の解説3つと無効・変更主張のまとめ

離婚が決まってから多くの人が一番心配することが養育費や慰謝料などのお金にまつわることです。
心配なのがお金を確実に支払って貰えるかどうかですよね。
お金に関しての取り決めを記した協議離婚書だけでは強制執行を行う効力はありません。
強制執行をかけて差し押さえをするためには、公正役場にて公正証書を作成したり、裁判所で判決等をもらう必要があります。
また、公正証書の内容は簡単に変更できないため、弁護士に相談して慎重に作成することが最適な方法です。
最初は相談が無料で出来る事務所もありますので、ぜひ活用してみて下さい。
思い当たる状況があれば、いち早く弁護士に相談し、どのような法的問題が発生し得るか・どのように対応すべきかを確認するのも一つの手です。
公正証書の取り消し・無効主張・公正証書の変更について知りたい方はこちらも読んでみてください
>>【関連記事】【公正証書で離婚】絶対に覚えて欲しい公正証書の役割と作成するときのポイント
>>【関連記事】離婚後子供に会えない!離婚後に子供に会うためにすべきこととは?